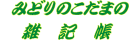
| 2024年11月 のメッセージ【遅れてきた彼岸日和な中秋編】 |
| ◆10月になっても、連日夏日で、まだ夏の名残り、ヒガンバナは、今年は遅れて出て来て寒露花に?キンモクセイは霜降の頃にようやく香った。季節の歩みは依然週回遅れだ。エコーの活動は、13日にサンデーすがたに活動として、広場周辺の園路の補修と野草圃場用の柵づくりを、19日の東畑は、湯出辺池周辺の草刈りを、突然の豪雨に見舞われながらも、かろうじてコンプリート、26日には、ひょうたん島コースの間伐作業で、アラカシの高木などの伐採作業と次回のあそび隊の間伐体験の為の草刈りなどを行った。 ◆久しぶりの雨の後、北風が吹いた20日の朝「広場のゲートで大きな木が倒れていて歩きにくいですわぁ」とハイカーから。現場へ向かうと、アカメガシワの大木が根元から折れて、危うく和田さんのウメの木に覆いかぶさる程の、ぎり傍に横倒しに。ここにこんなアカメの大木があったとは、先駆樹種のアカメガシワでこれ程の大木になるとは、この広場と30年近くの付き合いになるが、まだまだ驚く事はあるものだ。 ◆今年になってちょっとした天候の荒れで、あっさり倒れてしまった大木が目立つ。その特徴は根上りではなく、幹折ればかり。戦後80年近く経ち、今ある大木は、恐らくは、その頃若木であったリアル里山時代の生き残りの木なのだろう。推定樹齢100年前後か。これ程長い時間、人の手が入らず、野放図に成長して来た事は、歴史的にも、かつて無かったはず。それ故、自身の太枝を支えるには腐朽した根元では荷が重くなっての事とかと思われる。 ◆ナラ枯れの嵐が吹き荒れた頃、市民による里山の高木林管理の問題と言われたものだが、ひょっとして、高齢化した高木林管理の危うさという、こちらの方が今後問題かも知れない。大木化の弊害は、低木層の花木の日隠だけでなく、激甚化する気象現象や来る大地震への備えとして、国土強靭化を言うなら、これはもはやプロの出番の時期なのかもしれない。 ◆25日朝「檻にシカ入っとる」と連絡が。センター横の河原に向かうと若いシカが入っていた。昼過ぎになってから、若い女性と親方ら3人の猟師が来た。電流テスターのお化けの様な道具で感電死させる為に現場に向かう。上からその様子を見ていると、猟師の接近で、シカは何とか逃げようとして、檻に向かって渾身の体当たりを、次の瞬間、フラ〜っと仰向けにのけ反って、そのまま崩れる様に倒れ込んだ。脳震盪を起こした様で、その後、猟師はそのまま労せず槍の様なテスターの針を触れさせスイッチオン。あっけない結末となった。 ◆四肢を結わえて上げて来たら、鼻筋は傷だらけで、ゴンボ角が生えかけの若いオスだった。この日は他にも東山でも2頭処理があるとか。やっぱり実際に見ていると、可哀想、気持ちの良いものではない。だが、バランスの崩れた山も、この哀れな一頭、一頭の犠牲の積み重ねで、何とか維持管理している訳か。哀悼。 (中川勝弘) |